ギルブの法則
「ギルブの法則」という言葉をご存知ですか?
これは、「どんなものでも、計測しようと思えば必ずできるし、測定しないでいるよりもずっとよい。」というものです。
トム・デマルコとティモシー・リスターによる名著「ピープルウエア」(日経BP社)で紹介された言葉です。
それが「食べたらネット」に何の関係があるって?
私は、以前の職場でソフトウェア開発プロセス(業務手順)の改善に取り組んだことがあります。
ソフトウェア開発のように属人的な要素が大きいプロセスでは、計測(定量化)がとてもやりにくいものです。
製造工場の効率アップであれば、現状のプロセス効率はストップウォッチを持って測ることが出来ますが、ソフトウェア開発では同じ人が同じプログラムを開発するのでも、その時の状況によって生産性は格段に違います。
また、ソフトウェアの生産性は、人により5倍ぐらい違うとも言われています。
このようなあいまいなプロセスは、計測不可能と思われますが、改善をするためには、現状の把握のために計測が不可欠です。
そこで使われる言葉が、ギルブの法則なのです。
自動制御の世界では、「計測できないものは制御できない」と言われています。
おいしい天ぷらを揚げるために、油の温度は180度が良いとされています。しかし、現在の油の温度が分からなければ、おいしい天ぷらを揚げることは困難です。多くの人は、衣の一部を落とした時の泡の様子などで間接的に油の温度を測定しています。
最近では、温度センサーのついたクッキングヒーターがあって、自動的に適温を保ってくれるそうですが、人間の体重は自分でコントロールするしかありません。
経営手法・品質管理手法のひとつに「シックス・シグマ」というものがあります。
シックス・シグマではMAICプロセスと言われる手順で経営目標・品質目標の達成を目指します。
ここでそれぞれの頭文字は、
M:Measurement -測定
A:Analysis -分析
I:Improvement -改善
C:Control -定着への管理
を意味しています。
この手法の特徴は、最初に測定があるということです。
現状の把握のためにも、分析・効果測定のためにも計測が重要だということがわかります。
ダイエットに取り組むためには、食事・運動・体重/体組成を計測する必要があります。
このうち、運動の記録は、歩数計というツールがあります。体重/体組成の記録は体重/体組成計がありますね。
しかし、食事の記録はこれまで決定的なものがありませんでした。
私自身がダイエットに取り組んでいたとき、毎日腹囲、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、歩数、便通の状況を記録していました。
しかし、食事の記録についてはカロリー値などに定量化することが出来ずに諦めていました。
最近ではお弁当などのカロリー表示はあるのですが、自宅で食べたものについてはカロリーブックを読みながら自分で計算するしかありませんでした。
携帯電話で写真を撮ってメールで送ると分析してくれるサービスもありますが、継続的に毎食を分析してもらおうとするとコストがかかって現実的ではありません。
「無いなら自分で作ってしまえ」という訳でもありませんが、そのような想いが「食べたらネット」開発のきっかけになったのは確かです。
EDIT


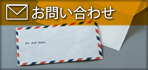
![Watch & Shot - Webビジネスのコンサルティング・執筆のEyedo[株式会社アイドゥ]](http://www.eyedo.jp/ws/images/ws_title.jpg)