特集「突然の危機に慌てない経営者になるための1日間」~ 自社が生き抜く「BCP」に触れよう ~
| 掲載誌 | 雑誌「アクセスさいたま」(財団法人埼玉県中小企業振興公社) | |
|---|---|---|
| 掲載年月 | 2006年7月 特集 | |
| 執筆者 | 株式会社アイドゥ 代表取締役 井上 きよみ (中小企業診断士) | |
最近「リスクマネジメント」や「BCP」といった言葉を耳にする機会が増えました。地震、台風、洪水など深刻な自然災害や、火事、テロなどの人災があちこちで報道されています。
そうでなくとも競争激化の波が、中小企業を容赦なく叩く今日、「物騒な世の中になった」と嘆くだけでなく、それをチャンスに変えるためにも、経営者の皆様、ぜひ夏休みの1日で事業存続をまじめに考える「BCP事始め」にしませんか。
事業継続計画は最も家族に貢献する
今までの災害対策では、防災と人命保護に重点が置かれていました。皆様の会社やお子さんの通う学校で、避難訓練を実施したり、緊急連絡網を整備して配布したり、ということからも納得がいくでしょう。しかし、その後をどうするかは、その時になってから考える、という具合ではないでしょうか。
今回話題にする「BCP」とは、「Business Continuity Plan」の略で「事業継続計画」と訳されます。「その後」をどうするかまで踏まえた所が、今までの防災とは大きく異なります。
では、なぜ、そのBCPが家族に貢献するのでしょうか?
人は「命」の確保ができると、次は「安全」、そして「生活」の確保と短期間のうちに最重要事項が移りゆきます。大地震が発生した時、BCPによって取るべき行動が明確になっていたら、家族か会社かで悩む必要はなく、その迅速さが両方を救うことになります。人命の無事が確認された後、復旧計画が整っていれば、社員や家族を路頭に迷わす可能性を格段に減らせます(図表1)。
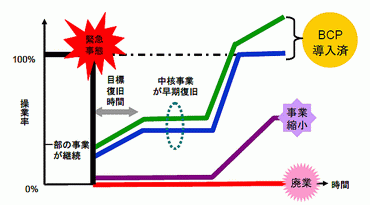
|
| 図1・企業の事業復旧に対するBCP導入効果のイメージ |
BCPは最も家族に貢献する、とは、私自身が一経営者として切実に感じた点です。ですから、単なる流行言葉と思わずに、まずは1日、BCPに触れ、BCPを考える時間を作ってみましょう。
「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」
これは、京セラ創業者の稲盛和夫氏の有名な言葉。もちろん、この言葉の本来の意味はBCPを意識したものではありませんが、その精神はBCPにも通ずるものがあります。特に日々の仕事に追われる経営者ほど、「もしもの時は・・・」と毎日毎日心のどこかで気にかけていても、単に思うだけで、何らかの行動に移すことは、ほぼ皆無でしょう。時間がないだけではなく、起こってほしくないという恐怖から無意識に目をそらしているのです。
しかし、BCPを検討することは、心の漠然とした恐怖を整理することになり、経営者自身の不安を取り除く効果もあります。平時には経営者にとって、それが最も意義あることかもしれません。
BCPを見渡す
中小企業にとってのBCPとは、経営者が頭の中に描いている、緊急時に会社がどういう状況になり、どう行動すべきかのイメージを、筋道立てて検討し、事前に対策を整理したものです。それを全員で共有し、日常的に運営していくことで、企業が緊急時に生き抜く手助けとなります。
平常時からBCPを準備できる企業は、顧客や関係者から高い信頼が寄せられ、事業の拡大につながる可能性さえあります。
BCPの策定・運用から発動までの流れは、図表2のようになります。
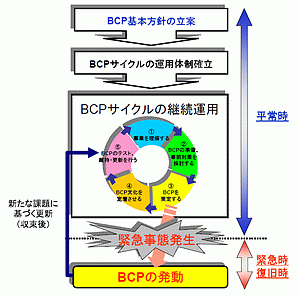
|
| 図2・BCP策定・運用、緊急時の発動についての全体像 |
BCPの策定にあたり、まずは、
- BCPの基本方針立案
- 運用体制の確立
ここで、BCPの特徴を5つあげます。
- 優先して継続・復旧すべき中核事業を特定
- 緊急時における中核事業の目標復旧時間を設定
- 緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議
- 事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意
- 全ての従業員と事業継続についてコニュニケーションを図る
「中小企業BCP策定運用指針」を利用しよう
私たちがBCP策定を進めるのに、中小企業庁が出している「中小企業BCP策定運用指針」(図表3)が役立ちます。BCP策定方法の解説、記入シート等があり、Webページの内容は「ダウンロード」メニューから、Word・Excel、PDF形式でダウンロードできますので、必要に応じて活用しましょう。
しかし、その指針自体は相当なボリュームで、一通り読むだけでも時間がかかりますので、この様式を使いながらも、本特集では必要な所のみをかいつまんで解説します。
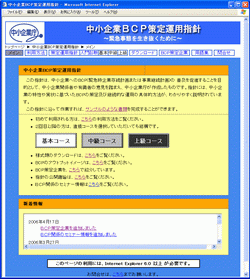
|
| 図3・中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」トップページ |
自社BCP検討の前に
まずは「入門診断」(図表4)で事業継続能力の事前チェックをしましょう。同じものがWebにもあり、判定を自動的に出してくれます(図表5)。
| 設 問 | 初回チェック | 1日後チェック | |||||
| はい | いいえ | 不明 | はい | いいえ | 不明 | ||
| 人的資源 | 緊急事態発生時に、支援が到着するまでの従業員の安全や健康を確保するための適切な災害対応計画を作成していますか? | ||||||
| 災害が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたは従業員と連絡を取り合うことができますか? | |||||||
| 定期的に避難訓練を実施していますか? | |||||||
| 初期救急や心肺蘇生法の訓練を受けた従業員がいますか? | |||||||
| 物的資源(モノ) | あなたのビルは自然災害の衝撃に耐えることができますか? そして、ビル内にある機器類はその衝撃から保護されますか? | ||||||
| あなたのビルへの部外者の侵入を阻止するために、外部塀やフェンスおよび入口ドアや窓の保全を定期的にチェックしていますか? | |||||||
| あなたの会社周辺の地震や洪水の被害に関する危険性を把握していますか? | |||||||
| あなたの会社の設備の流動を管理し、目録を更新していますか? | |||||||
| 物的資源(金) | 1週間または1カ月間程度、事業を中断した際の損失を把握していますか? | ||||||
| あなたは、災害後に事業を再開させる上で現在の保険の損害補償範囲が適切であるかどうかを決定するために保険専門家と相談しましたか? | |||||||
| 事前の災害対策や被災時復旧を目的とした融資制度を把握していますか? | |||||||
| 1か月分程度の事業運転資金に相当する額のキャッシュフローを確保していますか? | |||||||
| 物的資源(情報) | 情報のコピーまたはバックアップをとっていますか? | ||||||
| 自社オフィス以外の場所に情報のコピーまたはバックアップを保管していますか? | |||||||
| 操業に不可欠なIT機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法がありますか? | |||||||
| 主要顧客や各種公共機関への連絡先リストを作成していますか? | |||||||
| 事業継続 | あなたの会社が自然災害や人的災害に遭遇した場合、会社の事業活動がどうなりそうかを考えたことがありますか? | ||||||
| こうした緊急事態に遭遇した場合、どの事業を優先的に継続・復旧すべきであり、そのためには何をすべきか考え、実際に何らかの対策を打っていますか? | |||||||
| 長期間の停電や電話の輻輳する、コンピュータシステムがダウンする、取引業者からの原材料の納品がストップするなどのケースについて、代替手段を用意できていますか? | |||||||
| 社長であるあなたが出張中だったり、負傷したりした場合、代わりの者が指揮をとる体制が整っていますか? | |||||||
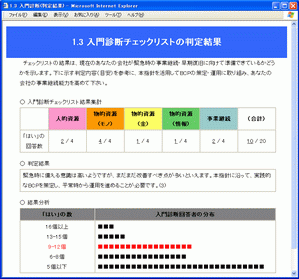 |
| 図表5・Webでの入門診断の判定結果例 |
次に、本特集のゴールとなる、BCPのアウトプットイメージを確認します。ダウンロードページ内「(3)アウトプットイメージ」の「サンプル(基本コース)」(図表6)を印刷するとよいでしょう。これを見て、BCPにはどんな項目を盛り込めばよいか、それらを盛り込むことでどんなメリットがあるかを考えてください。
「こんなのを作るのは、私には到底無理」「1日でできるわけない」と尻込みしないで、今日は、すぐにわかる箇所のみ埋めることを目標とし、見本はそれを手助けするものとして活用しましょう。
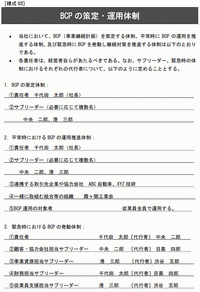 |
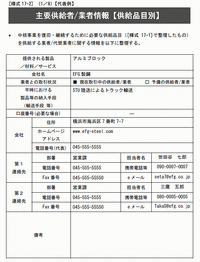
|
| 図表6 : BCP記入シートの一例(基本コースのサンプル)ダウンロードページのURL | |
最低限必要な「基本コース」を策定しよう
「中小企業BCP策定運用指針」ではレベルにより、基本・中級・上級の3コースを用意していますが、今回は最低限必要なBCPをできるだけ「早く」「簡潔に」作る「基本コース」で実施します(図表7)。
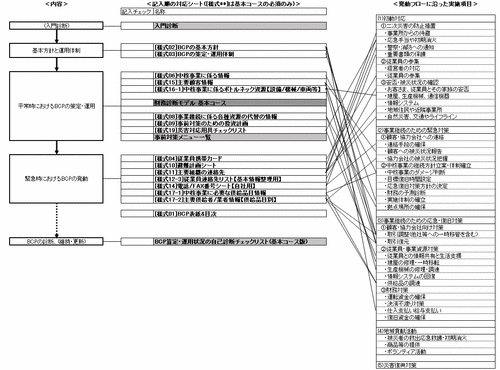 |
| 図表7・BCPの策定・運用に沿った記入シートと、発動フローとの関連 (「中小企業BCP策定運用指針」の内容より筆者が作図) |
それでも、途中で悩んだり考え込む箇所に多々出合うと思いますが、とにかく一通り短時間で進めるために、以下の3つを提案します。
- 経営者の主観でよい
- 書き方に迷ったら、すぐに見本 を参考にする
- 不明箇所には、
- ○:会社に行けばわかる
- △:スタッフに聞けばわかる(その人の名前をメモ)
- ×:時間をかけなければわからない。
それでは、「BCP様式類(記入シート)」をダウンロードしましょう。(「一括ダウンロード」が便利です。)シートの記入は、図表7に沿って進めていきます。
BCPの基本方針と策定・運用体制
[様式02]BCPの基本方針
BCPで重視したい以下の4点を踏まえましょう。
- 企業同士の助け合い
- 緊急時でも商取引上のモラルを守る
- 地域を大切に
- 公的支援制度の活用
[様式03]BCPの策定・運用体制
経営者自らの率先が何よりも重要で、リーダーシップを取るようにしましょう。合わせて全従業員が周知できるよう、考慮します。
中核事業の理解と被害の評価
[様式06]中核事業に係る情報
[様式15]主要顧客情報
会社の存続に関わる最も重要かつ緊急性の高い事業を「中核事業」とし、特定します。いくつかある場合は、優先順位を付けます。そして、中核事業に付随する「重要業務」を考えます。
[様式16-1]中核事業に係るボトルネック資源【設備/機械/車両等】
次に「ボトルネック資源」と呼ばれる、中核事業・重要業務に必要な資源をピックアップします。
合わせて取引先との調整、自社が他えら得る期間の両方を考慮し、中核事業の目標復旧時間を決めます。
財務状況の分析
被災に備えるには、よく1ヶ月分の月商を資金として用意するように言われますが、ここでは、資金建物・設備の復旧費用や事業中断による損失を概算し、現状把握します。「財務診断モデル 基本コース」をダウンロードしましょう「シート1」「〃2」の水色部分に数値を入れると自動計算されます(図表8)。
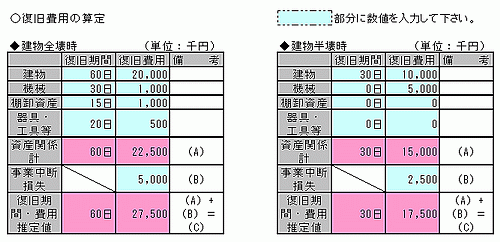 |
| 図表8・「財務診断モデル基本コース」の復旧費用の算定部分 |
[財務診断モデル 基本コース]
復旧費用の算定において、リース機器の場合、損害はリース会社に転嫁されます。
損害保険の代表例は火災保険ですが、この機会にどの災害に対し、どこまで補償するかをきちんと把握し、適切な損害保険を付けるよう検討しましょう。
「シート2」の手持ち資金の合計は、自力で賄える額です。
手持ち資金と復旧費用とを比べ、復旧費用の方が大きければ、災害時の融資制度などを調べ、キャッシュフロー対策を実施しなければなりません。
中核事業継続・復旧の準備と事前対策
[様式08]事業継続に係る各種資源の代替の情報
中核事業の継続・復旧でのポイントは、
- 必要な資源を緊急事態発生時にどのように確保するか
- 大きな影響を与える災害および資源に対し、事前対策を検討
[様式09]事前対策のための投資計画
事前対策は、避難計画を作成するといった「ソフトウェア対策」と、施設を耐震化するような「ハードウェア対策」に大別できます。予算上の制約からも、まずはソフトウェア対策を確実に実施します。一方、ハードウェア対策は優先順位を付け、中長期計画に組み入れることが必要です。
[様式19]災害対応用具チェックリスト
[事前対策メニュー一覧](図表9)
これらも「転ばぬ先の杖」として、チェックしておきましょう。
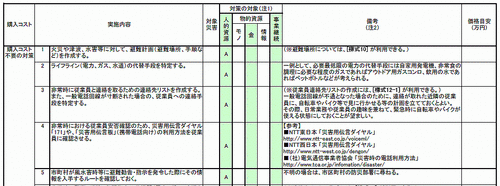 |
| 図表9・「事前対策メニュー一覧」の一部 |
BCPの発動基準
BCPの発動基準設定の目安は、中核事業に何らかの異変が起こり、早期対応しなければ、目標復旧時間内に復旧できないと想定できる時です。災害の種類と規模に応じて、発動基準を定めるのがよいでしょう。
発動フローは図表10のようになります。
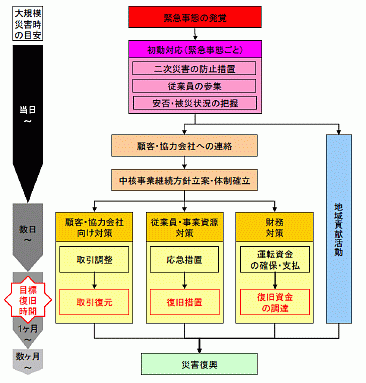 |
| 図表10・緊急時におけるBCP発動フロー |
BCP発動体制の明確化
緊急事態の発生時には経営者のトップダウンの指揮命令が重要となります。
[様式04]従業員携帯カード
[様式10]避難計画シート
[様式11]主要素式の連絡先
[様式12-3]従業員連絡先リスト【基本情報整理用】
[様式14]電話/FAX番号シート【自社用】
[様式17-1]中核事業に必要な供給品目情報
[様式17-2]主要供給者/業者情報【供給品目別】
BCP発動フロー(図表10)に示される手順ごとに、情報を整理し、文書化します(図表7)。
記入作業を終えて
[様式01]BCP表紙&目次
最後に目次にページ数を入れて、出来上がりです。
これで一通りの記入ができました。お疲れ様です。「結構埋まったなあ」「すぐにはわからないことだらけだ」等々、人それぞれに感想をお持ちでしょうが、どなたも事業継続に対する関心がにわかに大きくなったことでしょう。
今回の作業は、いわば「はじめの一歩」です。経営者自ら興味を持つことが最も大切で、今日の体験をきっかけに、従業員と一緒に「生き抜く」方法を考え、いざという時には実行してください。
BCPも他の計画同様、1回作ったら終わり、ではありません。ここからがスタートで、少なくとも年に1度は見直しをかけ、有効なBCPとなるように努めてください。そのための「自己診断チェックリスト」(図表11)も用意されています。
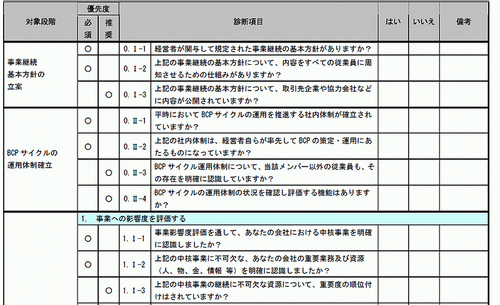 |
| 図表11・ 「BCP算定・運用状況の自己診断チェックリスト(基本コース版)」の一部 |
最後に、本日の最初に実施した「入門診断」(図表4)をもう一度やってみましょう。「はい」の増えた数が、何はともあれ今日の成果です。
EDIT
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 特集「突然の危機に慌てない経営者になるための1日間」~ 自社が生き抜く「BCP」に触れよう ~
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.eyedo.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/134



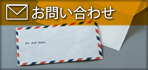
コメントする